取代のつぶやき2
仕訳が不安
その2まで終えたところで…

仕訳をする時、売上が右?左?、あっ、そうだった収益だから右だ…とか、左右どっちに振り分けたらいいのか、まだまだ不安です。

いやいや、今の段階ではまだまだそれで全然OKですよ。まだ簿記を始めて数日。
そんなにテンポよく仕訳がすらすらと書けるわけありません。取代さん、全然心配なしですよ。
例えばです。「商品100円を現金で売り上げました」
この仕訳、どうでしょう。

売上が収益なので…右ですよね?そして現金が左です。
なので、
現金 100 / 売上 100 ですかね?

正解です。できるじゃないですか。大丈夫そうですね。
一応、私が簿記を勉強し始めたころのやり方を紹介しておきますね。
今後、困ったときに思い出してください。
このやり方、その1の記事内でも少し説明していますが、改めてここでも触れておきます。
上の仕訳の場合、現金が出てきましたね。現金は資産なので増えたら左ですよね。
まずはこれだけを強烈に覚えちゃってください。
とにかく現金が増えたか減ったか、それだけに注目です。
現金が増えた!その時点で「現金 ××/○○ ××」と現金を左側に無条件に書いちゃいます。
ここは考えるとかそういうレベルじゃなく、もう「反射」というレベルでできるようになっておくと良いです。
分かる科目からすぐに書く!を鉄則にして行きましょう。
その後、残った科目(今回は売上)を反対側に書く。
そんな感じでいいんじゃないでしょうか。
なので、まずは参考書や問題集で、現金が出てくる仕訳問題だけを抜き出して集中的に書いてみると良いと思います。
そうして、現金が無意識に左右どちらかに仕訳できるようになったら、次は、例えば、売掛金は資産だよね…資産だから現金と同じような動きになるな…という感じで、1つずつでいいので反射的に対応できる科目を増やしていくんですね。

まずは「現金」ですね。
確かに一番身近で考えやすいですもんね。やってみます。

現金 ××/ と書いたあとに、売上を反対側に当てはめるじゃないですか。
その後にじっくり考えるんです。売上って右で良いんだっけ?って。
そうすると収益が増えてるんで、右で大丈夫だなとなって、これで仕訳完了です。
必ずここまで考えて、確かめて…という事をしてくださいね。
そうすることで少しずつ記憶に結びつくので。
また、仕訳が完成したら最初のうちはもう一度、左右の科目を確認しましょう。
資産、負債、資本、収益、費用の何が増えて、何が減っているのか。それぞれの科目が増えたり減ったりしたら、左右どちらに行くのか…そのあたりを毎回確認することで仕訳の上達につながります。
最初はいちいち時間がかかってしまうかもしれませんが、それが仕訳上達の近道だと思ってください。
資産、負債、資本、収益、費用の5つのカテゴリが増えるのか減るのか合計10パターンしかないんですよ。
しかも資本の科目は期中ほとんど動かないし、収益、費用も、増えることはしょっちゅうですが、減るという仕訳をすることは頻繁ではありません。

だから、そう考えると、6パターンくらいしかないんですよ。
気軽に考えちゃいましょう。

はい、がんばります!
簿記試験での勘定科目と考え方

あと気になったのが、デンタクさんが「その1」の費用の説明の中で「事務用品費」って使ってたんですよ。確か、ボールペンとかは事務用品費だって言ってましたよね。
でも、私の使ってる参考書には、貸借対照表と損益計算書のひな形みたいなのが載ってて、そこに科目がズラッと並べて書いてあるんですけど、費用のところに「事務用品費」って勘定科目、無かったんですよね。
これ、覚えないとダメですか?

とてもいい質問だと思います。
私も簿記の勉強を始めたころ、勘定科目ってひとつひとつ、一言一句間違いなく覚えないといけないのかな?と不安でした。
基本的には「こういう時にはこういう科目を使う」というルールはあります。
また、例えば電気代とか水道代とかは「水道光熱費」みたいに、もう誰が見ても決まって使う勘定科目もあります。
ただ、ボールペンは○○費じゃないとダメ!とか、会社で使うティッシュペーパーは何費にしたらいいの?とか、細かいところまでは正直なところ、あまり気にしなくていいです。

気にしなくていいって言われても、試験の時どうしたらいいの?って不安になる人もいますよね。きっと。
私も不安です。

そうなんですよね。
じゃあ試験の時どうするの?どうやって判断するの?ってことになっちゃいますよね。
ちなみに、簿記3級の試験では、「この中から勘定科目を選んで使ってね」みたいな科目の一覧が示されていたりします。
ネット試験だと、仕訳の問題を解くときにプルダウンで選択する科目が出てくるようですね。
その選択肢の中に「どの科目を使ったらいいかな?」と迷ってしまうような科目が複数登場することはまずないと思います。出題者の方々が引っかけ問題として判断に迷う勘定科目を出すことはありますけどね。
ただ、それは明確に意図があって出される勘定科目なので、しっかり勉強していれば判断に迷う事は無いようになっているはずです。
例えば先程のボールペンのお話、私は事務用品費って言いましたけど、簿記の試験だと、消耗品費になるのかな…と思いますが、変な話、事務用品費でも、消耗品費でも、もっと言うと雑費でもいいんじゃないかと思うんですよね。
で、試験問題の時に、そんな風に迷っちゃうような選択肢がいくつも並ぶかと言えば、そんなことないと思います。
また、もし迷いそうな勘定科目が選択肢で並んでいたら、自分が一番近いかなと思う科目を選ぶしかないと思います。(ただそのケースは滅多にないと思います。)
ここからは今後、皆さんが簿記を勉強されたうえで、実務として使っていくときの話も含めて書いていきますね。長くなりそうなのでちょっと区切りを変えましょうかね。
使える簿記としての勘定科目
多分、専門学校の授業であったり、参考書などではここから先の話はあまり出てこないと思います。
試験で点を取ることに集中(優先)されたい方は読み飛ばしてもらっても全然OKです。
では行きますね。
先程、ボールペンは事務用品費でも、消耗品費でも、雑費でもいい…と言いましたが、皆さんからするとなんて曖昧で適当なことを言うんだと思われることと思います。
でも、それくらい柔軟に考えると言うか、ちょっとラフな感じでかまえているのが丁度いいのかなと思うんですよ。
私は以前税理士事務所に勤務していたことがあるんですが、その時にお客さんから送られてくる帳簿には、色々な勘定科目が登場しました。
もちろん決まりきった科目もありますが、中には独特な勘定科目を使って仕訳をしてくるお客さんもいます。
要は、どんな勘定科目を使うかは意外と自由という事です。
どういうことか、説明しますね。
簿記の目的は最終的に貸借対照表や損益計算書を作ることだと言いました。
その貸借対照表や損益計算書、特に小さな企業が何に使うかと言うと、主に税金計算が目的になってくるんですね。
税金の計算をする時、かなりザックリ言っちゃうと、税金計算に影響を与える特定の費用でない限り、費用がどの勘定科目になっていてもあまり影響がないんですね。
収益-費用=利益という大前提をベースにして税金の計算をしていって、極端に言えば費用の中身によって税額が変わることって、特に小さな会社ではあまりありません。
一部気にしないといけない科目もありますが、費用じゃないものを費用にしたりしていない限り、そんなに目くじらを立てることもないんですよ。
費用になるべきものが、費用の仲間に入っていればいいというか。
ものすごく極端な言い方ですが、そんなイメージで良いと思います。
先程どんな科目になっていてもそんなに気にしないと言ったのはそういう事です。
次にこんなことも考えられます。どんな事業をしているかによって同じものでも使い方とか違いますよね?ってお話です。
どういう事かと言うと、例えばお掃除に使うスポンジがあったとします。
皆さんがお家で使うようなものを想像してください。
一般的な会社さんが、事務所や社内のどこかをお掃除する時、スポンジ使いますよね。別になんてことないです。皆さんのお家と同じ。
その場合勘定科目は普通に消耗品費です。
でもこれが、お掃除業を主な業務としている会社だったらどうですかね。
スポンジって、ある種の商売道具ですよね?
でも、このスポンジも同じスポンジなので、消耗品費として全然OKなんですよね。
私などは、お掃除業じゃない、全然普通の会社が事務所のお掃除に使うためのスポンジと、お掃除業をしている会社さんのスポンジは、感覚として勘定科目を分けて使いたいな…と思っちゃうかもしれません。
お掃除業の会社の社長さんが、仕事道具としてスポンジにどれだけお金を費やしたか知りたいってなった時に、他の消耗品類とお掃除業で使うスポンジがまぜこぜに全部「消耗品費」に入っていたら、判断がつかないじゃないですか。
そんな時、会社の経理担当者さんの腕の見せ所なんですよ。
新しい費用の科目を作って、そこにスポンジや洗剤の購入費用を計上していく。
そうですね、例えば「掃除用品費」とでもしましょうか。そんな科目を作ったりします。
簿記の試験では、「掃除用品費」なんて科目名、出てきませんよね。
でも、現実的には経理担当者さんがこのように自由に科目を作ったりすることがあるんですよ。
要は、その会社会社に合った勘定科目の使い方があるという事です。
このお掃除業の会社のスポンジや洗剤って、どちらかと言えば「仕入」に近かったりする感覚、分かりますかね。そんな感覚をわかってほしいなと思うんです。
例えば「掃除用品費」が特に多かった会計期間は、売上も自然と伸びているかもしれませんよね。
逆に、売上があまり多くないのに、「掃除用品費」が多かったなんていう会計期間は、なんか無駄に掃除用品を使っちゃったのかな?とか、そんな風にちょっとした分析もできちゃったりするんですよね。
これこそ使える簿記じゃないですかね。
簿記の目的は貸借対照表や損益計算書を作ることだと言いましたが、上記のように、経理担当者さんの工夫によって、実際のお仕事の中で数字が活躍してくれることもたくさんあります。
そんな風に、使える簿記にして行くことが経理担当者さんの「腕」なんですよね。
ここまでお話したら、勘定科目の使い方が柔軟であったほうがいろいろ便利かもしれないよね。って思っていただけるのかなと思います。
決まりきった形で使う勘定科目ももちろんあって、それはそれで正しい使い方をするべきですが、中には柔軟さが普段の仕事の中で帳簿を活かせるチャンスになりますよと、そんなお話でした。
何となく雰囲気だけでも理解してもらえると嬉しいなと思います。
取代さんのつぶやきだったのに、なんだか私デンタクが語るコーナーになっちゃいましたね。
長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。

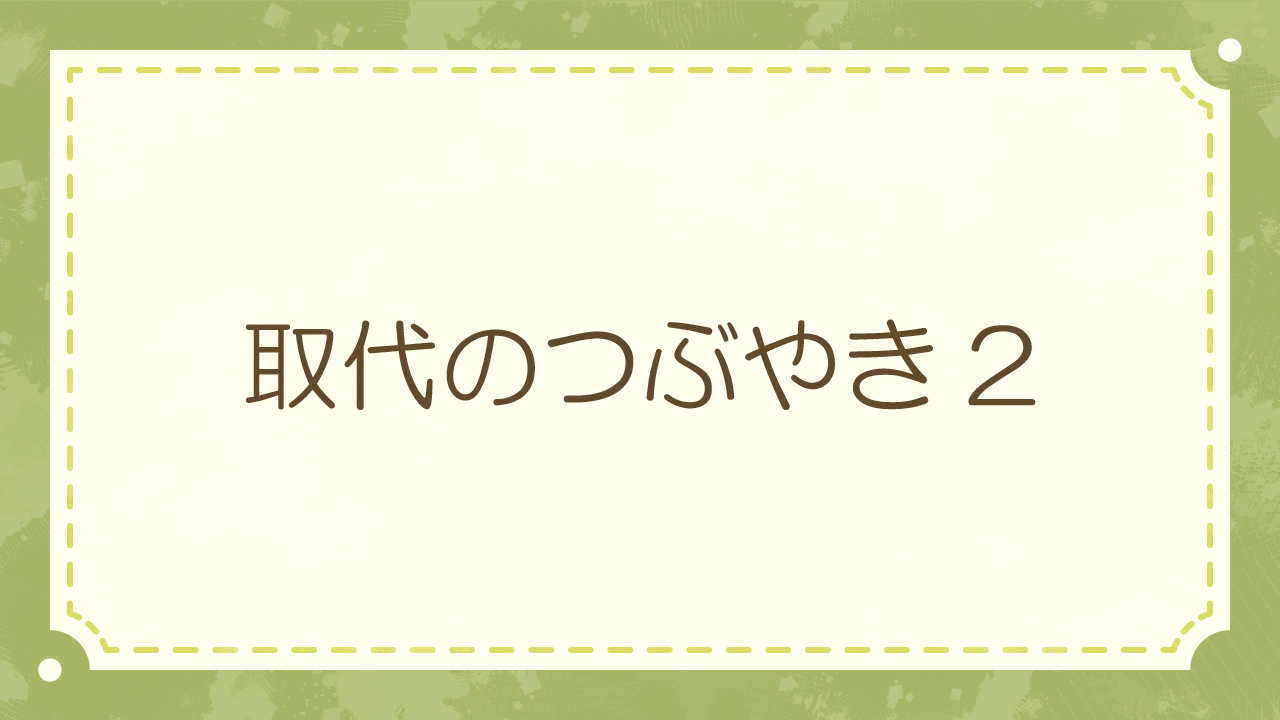
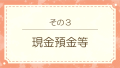
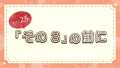
コメント